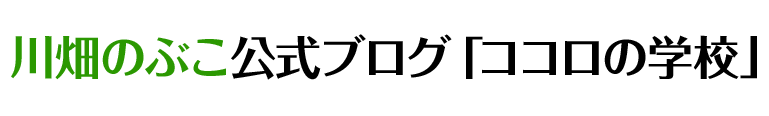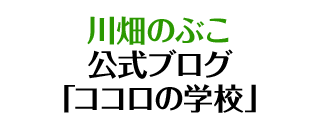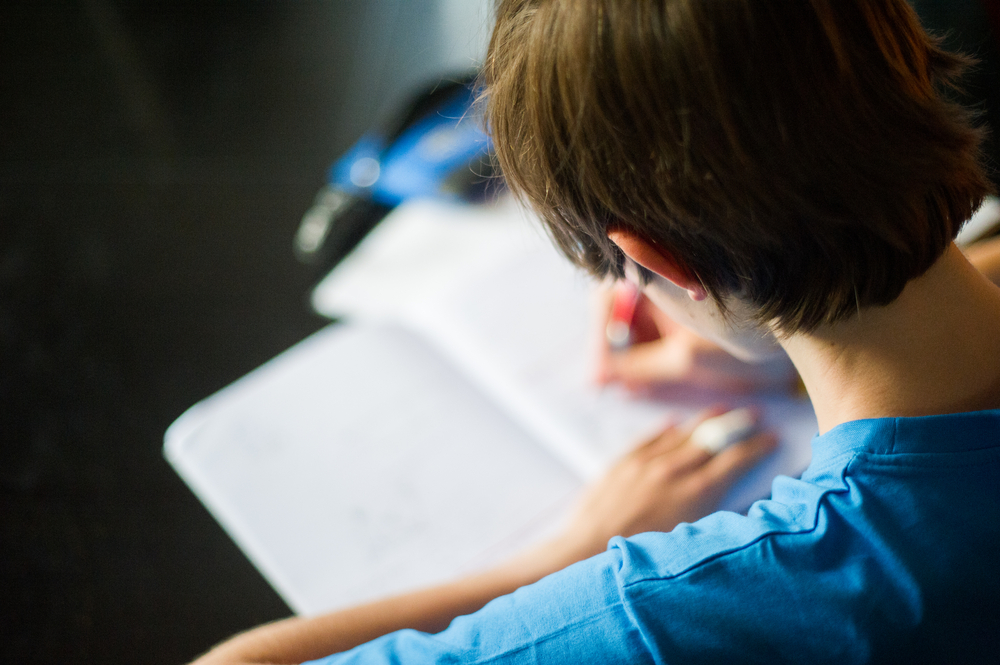Q:父は7年前に、母は4年前に他界し、
私(独身)はその実家(一軒家)に引き続き住んでいます。
私は3人姉妹の真ん中で、
姉と妹は結婚してそれぞれ家庭を持っています。
実家に住んでいる私が主に親の遺した遺品を整理していますが、
4年になる現在もなかなか終わりが見えてきません。
特に、母はいわゆる超タメコミアンで
実際に「賞味期限が昭和の日付の食品」や
「今年35歳の妹が生まれた時の、友人たちから貰った出産祝いの
全く手をつけてないもの」が、母亡き後に見つかり、泣きそうになりました
(情けなくて)
バックヤードから、母の衣類の尋常じゃない量がわんさか出てきて、
何度埃でむせたことか…
私は、ここで「人間の命はモノより短い」
「溜め込んだモノのツケは、本人でなく残された者が背負うものだ」
ということを思い知り、断捨離の大切さを改めて実感したのであります。
「そんなに、遺品整理が大変なら業者に頼めばいい」という意見もありますが、
私としては本音はそうしたいのですが、それは現実難しいです。
というのは、嫁いで行った姉妹の存在です。
実際に母のものと思って処分した本棚が、
実は姉のものだったりしたこともあったりして、
処分できるものの線引きが曖昧なのです。
現実、遠方だったり、子供が小さかったり
配偶者の仕事の都合上、ウチになかなか来てくれなかったりするので、
相談もままならないです。
そして、母の遺伝子を引き継いだかのようなタメコミアンの姉妹で、
姉にいたっては、嫁いで10年になるのに
部屋一つ分埋まるくらいの荷物がまだ残っています。
「もう嫁いで行ったのだから、なんとかしてほしい」と言っても、
「ウチは転勤族で、そんなに広い家に住めないし、いつ引越しになるか
わからないから、持って行くことはできない」
「近いうちに、姑と同居する二世帯住宅を建てる計画がある。
そのときに持っていく」
と、言いながら、その建設予定地より、どんどん遠いところに、
転勤が決まっていきその計画が実行できるめどなんていつのことやら…
現実に姉が置いていった荷物が私の生活スペースを占領しているので、
「他人のものは勝手に捨ててはいけない」の断捨離の鉄則を守ってるにしろ、
姉のモノを隅の方にまとめておいて、私のスペースを作ろうとしては、
「私のモノをぞんざいに扱わないで!」と怒られる始末…
私は、「自分の身の回りの事で精一杯なので、
それ以外のモノにまで気を使う事はできない!」と言いますが、
「それは自分勝手」と言い返されます。
「妹の生活スペースをおびやかしてまでも、
10年も家を物置にしている方が自分勝手」と腹の底では言いたいところですが、
水掛け論になるだけなので、こらえています。
断捨離は素晴らしい片付け法とは思ってますが、
私ひとりではどうしようもないことを痛感しています。
私自身のモノの断捨離は、殆ど済んでます。
そして、一日も早く家の整理を終わらせたくて、
今年に入ってから、ほとんど遊びに行ってません。
平日は仕事、土日祝日は片付け。
五月の連休もずっと片付けしてました。
気がついたら今年も半分が過ぎていきこのまま年末になりそうです…
たまに少し遊びに出掛けても家の事が気になって、楽しめません。
このまま片付けばっかりして過ごすのは嫌です。
嫌ならやめてしまえばいいかもしれませんが、
やめたら汚部屋、ゴミ屋敷の生活が待ってるだけで、
それはもっと嫌なんです。
アドバイスがあればよろしくお願いします。
【まこと・41歳・会社員】
―――――――――――――――――
A:
FROM 川畑のぶこ
まことさんとご姉妹とのモノを介したバトル。
なかなか一筋縄ではいきませんね。
そう、人は相手を支配するときに
相手の罪悪感に漬け込むという術を知っています。
「あなたに思いやりがあるのなら取っておけるでしょう」
「相手をリスペクトするならそのままにしておくでしょう」
といった具合に。
その際、自分のモノで苦しんでいる相手のことは想像ができず、
ひたすら被害者意識が働いてしまうのですね。
整理すること=悪
取っておくこと=善
という不文律が根底にあることと思います。
まことさんの姉妹はお二人ともタメコミアンとのことで、
モノが溢れていることに慣れていらっしゃるので、
そのことで苦しむ人のイメージができにくいことが考えられます。
ですので、本当に大変で苦しんでいるのだということを知ってもらうために、
口頭ではなく、手紙で伝えてみてはいかがでしょうか。
また、モノを溜め込み、そのことで自分を満たそうとする傾向がある人
というのは、自分の持ち物を己の延長線上のように考えてしまい、
相手がそれを大切にしてくれるか否かで
相手が自分を認めてくれているか、または受け入れてくれているか否か
を図ろうとすることがあります。
これは無意識のうちに行われています。
まことさんは、不要になったモノを整理しようとしているだけなのに
「私が不要だというの!」と、モノと自分を同一化してしまっている状態ですね。
また、この時、自分が丁寧にそれらのモノを扱っていないことは
棚上げとなっています。
まことさんは、あくまでも本人が丁寧に扱わず、放ったらかしにしているものを
整理したいということを伝えているのであり、姉妹を大切にしないということではない
ということをはっきり伝えておくことは大事なプロセスであると思います。
まことさんは、ご姉妹のことは大事にされていると思いますので、
(それ故にこのことに真摯に向き合い、悩んでいらっしゃることと思います)
そこは自信を持って良いと思います。
モノを取っておくことで、相手への思いやりやリスペクトを表現したり証明したり
する必要はまったくありません。
今ご自身がこのことでとても困っていることを、
この問題をできるだけ早く解決したいことを、
そして、姉妹のことは大切に思っていることを、
誠実に伝えてみてはいかがでしょうか。
まことさんがご実家をご両親の遺産として全て相続されている場合は、
ご実家のスペース全てを自由にされたら良く、
ご姉妹のものはそれぞれの住まいに送ることが健全ですが、
姉妹3人が3分の1ずつ相続しているのなら、
ご姉妹にもその空間を自由に使う権利はあります。
(たとえ物置にしたとしても)
その場合は、どこからどこを物置として使うかということも
話し合ってみてはいかがでしょうか。
そしてそこに「丁寧に」保管することを伝えてみてはいかがでしょうか。
ただし、開かずの間に埃や菌が堆積し、衛生状態が悪化したなら、
それはまことさんの健康や人生の質を落とすこともきちんと主張し、
それ故にどのように管理するかも話し合いをして
クリアにしてみることをお勧めします。
どうか、相手への敬意と愛情を持ってコミュニケーションをスタートしつつ、
主張すべきことは引かずに主張してください。
主張は決して批判ではありません。
PS
メンタルの整え方がわかる!人生が輝く!
川畑のぶこ公式メルマガ(無料)
ご登録はこちらからどうぞ♪
PPS
あなたが今抱えている『悩み』をお聞かせください。
毎週水曜の「断捨離」メルマガおよび、
毎週月曜の「ココロの学校」メルマガで、
川畑のぶこがお答えします。
ご質問はこちらからどうぞ。