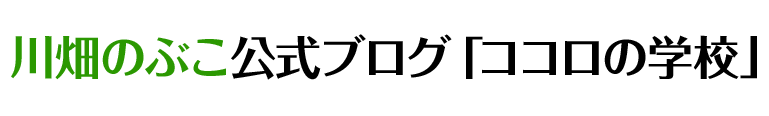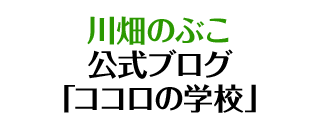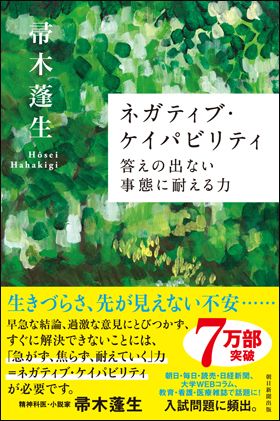Q:川畑先生こんにちは。
独身一人暮らしの兄69歳が
先日脳出血で入院しましたが、
元々血液の病気を持っているため寝たままで
日々弱っていっているように感じます。
13年前に夫を亡くしている私も、現在一人暮らしで、
兄とは月一回旅行に行ったりランチをしたりして
「食べられるうちに美味しいものをたくさん食べよう」
と食べることを楽しんでいました。
そんな兄が無言でベッドに横たわっている姿を見ると
「これはもう兄ではない」などと思ってしまいます。
そのくせ私はこんな状況なのにお腹が空くし
普通に食事をしているのです。
そして兄の家の冷蔵庫の中身の心配ばかり
しているのです。
兄がこんな状況にいるのになんで私は
こんな呆れるような考えや行動をとっているのか
自分のひとでなしさがこわいです。
そして今自分が生きて動いていることが
不思議でなりません。
なんとかまともな感覚を取り戻したいです。
助けてください。
【ヒロ・60代・女性・パート】
―――――――――――――――――
A:FROM 川畑のぶこ
ヒロさんの、お兄さんに寄り添い互いに支え合う、
思いやりある関係がうかがえるご相談です。
このように、
自分のことで思い悩んでくれる妹がいること自体、
お兄さんは幸せな人ではないでしょうか。
ヒロさんは、大切な兄が辛い状況なのに、
自分はなんでいつもどおりなのか、
まともではない、人でなしと
ご自身を責めていらっしゃるのですね。
私たちには、大切な人やものを失ったり
失いそうになったりするとき、
否認の心理がはたらくことがあります。
これは、現状を見ないようにすることで、
自分自身を平常に保とうとする
心理的な防衛機構です。
決して、薄情だから放っておいているのではなく、
つらすぎて現実から目を背け
自分を守ろうとする状態です。
それほどにお兄さんの存在がヒロさんにとって
大切なものであるのでしょう。
ですので、
どうかご自身を責めるのはやめてください。
人間はみな生まれた以上、
老いたり病んだり死んだりします。
適度な運動をしたり、
高級なサプリを飲んだりしても、
こればかりは誰にも避けられないものです。
そんな無常を受け入れ、
いつかその日が来るまでに、家族や友と
素敵な思い出をつくることができたなら、
それは豊かなことではないでしょうか。
お兄さんの見た目は変わってしまっても、
心の中にはきちんとその豊かな思い出が
保存されている、その見えない部分に
意識を向けてみてはいかがでしょうか。
「これは兄ではない」のではなく、
過去の若くて元気だったときの兄ではない。
それでも兄は変わらず私の兄であり、
過去は決して失われず、
すべて今に穏やかに含まれている
ということを思い出してみてください。
美味しい食べ物を愉しむ段階は卒業して、
これからはお兄さんと
穏やかで和やかな時間を過ごすという、
新しい関わり方でつながるよう
試みてはいかがでしょうか。
相手を思いやるということは、
相手と同じように苦しむということでは
ありません。
和やかで穏やかな関わりをするためにも、
ヒロさんはいつもどおり食べて、寝て、
健康を保つ必要があります。
良いサポーターであるためには、
まずご自身を整えることが重要なタスク
ということも覚えておいてください。
自分がどんな状態であっても
妹が和やかであるということは、
お兄さんに安心感をもたらしてくれることでしょう。
ーーー
★あなたが今抱えている『悩み』をお聞かせください。
ご質問はこちらから